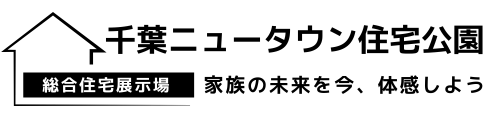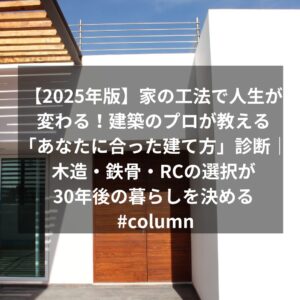この記事を読めば分かること
この記事では、新築住宅のコンセント計画について、以下のことが明確に理解できます。
- 現代家庭の「隠れた電力消費マップ」の作り方
- 家族の一日を追跡して見えてくる本当に必要なコンセント位置
- 部屋の用途別「最低ライン」と「快適ライン」のコンセント数
- 10年後のライフスタイル変化に耐えられる拡張性の持たせ方
- インテリアを損なわない「消えるコンセント」配置テクニック
- 予算と快適性のバランスを取る優先順位の付け方
はじめに
引き渡しから2週間後の朝、私は洗面台の前で立ち尽くしていました。
手にはドライヤー。でもコンセントには、電動歯ブラシの充電器が挿さっている。夫の電気シェーバーも充電したい。でもコンセントは2つしかない。
「一つ抜けばいいだけじゃん」
そう思うかもしれません。でも、これが毎朝なんです。毎朝、充電器を抜いて、ドライヤーを挿して、使い終わったら充電器を戻して。この15秒の作業が、365日続きます。
15秒×365日=91分25秒。年間で1時間半以上を、コンセントの抜き差しに費やしている計算になります。
「たった1時間半でしょ」と思いますか?でも問題は時間ではありません。問題は、毎朝この小さなストレスを感じることなんです。
マイホームを建てると決めたとき、私は夢を見ていました。真っ白な壁、広いリビング、アイランドキッチン。Pinterest で見つけた素敵な写真のような家。
でも、Pinterestの写真には映っていないものがあります。それが「生活の現実」です。
充電ケーブルが床を這う現実。延長コードが絡まり合う現実。「あと1口あれば…」と毎日思う現実。
新築から3年。私は今、確信しています。
家の快適さを決めるのは、デザインの美しさではなく、日常の小さなストレスがどれだけ少ないかだと。
そして、コンセントの位置と数は、その「小さなストレス」に直結する最重要要素なんです。
この記事では、私が3年間で学んだ「コンセント配置の真実」を、後悔と成功の両面から正直にお話しします。
誰も教えてくれなかった「電力依存度チェックリスト」
家を建てる前、設計士さんに言われました。
「お持ちの電化製品をリストアップしてください」
私は紙に書き出しました。冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコン、電子レンジ、炊飯器…。15個くらい書いて、「これで全部かな」と思いました。
でも、住み始めてから気づいたんです。本当の電力需要は、「大型家電」ではなく「充電が必要な小型デバイス」にあることに。
スマホ時代の隠れた電力消費
試しに、今この瞬間、あなたの周りを見回してください。
充電が必要なものは何個ありますか?
私が今、リビングで確認したもの:
- スマホ(私)
- スマホ(夫)
- タブレット(娘)
- タブレット(息子)
- ノートパソコン
- ワイヤレスイヤホン×2
- スマートウォッチ×2
- モバイルバッテリー
- Bluetoothスピーカー
- ワイヤレスマウス
- リモコン(充電式)
- 電子書籍リーダー
リビングだけで13個。これが現代の生活なんです。
部屋別「充電マップ」の作成法
家を建てる前に、ぜひやってほしい作業があります。それが「充電マップ」の作成。
方眼紙を用意してください。家の間取りを大まかに書きます。そして、家族全員の充電機器を、「どこで充電したいか」に従って配置していくんです。
我が家の場合:
玄関エリア
- 電動自転車バッテリー×2
リビング
- スマホ×4
- タブレット×2
- ノートパソコン×2
- ゲーム機×2
- リモコン類×3
キッチン
- タブレット(レシピ用)
- スマホ(タイマー用)
洗面所
- 電動歯ブラシ×4
- 電気シェーバー
- ドライヤー
寝室
- スマホ×2
- スマートウォッチ×2
- タブレット×2
- 電子書籍リーダー×2
子ども部屋(2部屋)
- 学校タブレット×2
- 自宅タブレット×2
- スマホ×2
- ゲーム機×2
合計で、充電が必要なデバイスは43個。
コンセントは最低でも40口以上必要という計算になります。
「同時充電率」という概念
でも、「43個全部を同時に充電するわけじゃないでしょ」と思いますよね。
確かにそうです。だから重要なのが「同時充電率」という考え方。
**就寝前(夜9〜10時)**は、充電需要が最も高まります。家族全員が自分のデバイスを充電し始めるから。この時間帯の同時充電率は、約70%。
つまり、43個のうち約30個が同時に充電される可能性があります。
これを部屋別に割り振ると:
- リビング:8口
- 寝室:6口
- 子ども部屋×2:各5口
- 洗面所:4口
- その他:2口
最低でもこれだけのコンセントが「同時に使える状態」で必要なんです。
「動線追跡法」で見えてくる本当に必要な場所
私が家を建てた後、最も後悔したのが「図面だけで判断した」ことです。
図面を見ながら、「ここにコンセント、あそこにコンセント」と決めていきました。でも、図面は平面です。人間の動きは、時間軸を持った立体です。
24時間行動ログの威力
住み始めて半年後、私はある実験をしました。
1日の行動を、15分単位で記録したんです。どの部屋にいて、何をして、どんな電化製品を使ったか。
その結果、驚くべきことが分かりました。
朝6:00-7:30(90分)
- 寝室→洗面所(往復3回)
- 洗面所での滞在時間:合計35分
- 使用した電化製品:ドライヤー、電動歯ブラシ、電気シェーバー、スマホ(音楽再生)
この90分の間に、洗面所のコンセントを5回差し替えていました。
夕方17:00-19:00(120分)
- キッチン滞在:90分
- 使用した電化製品:電子レンジ、炊飯器、電気ケトル、フードプロセッサー、タブレット(レシピ確認)
- コンセント差し替え回数:3回
夜20:00-22:00(120分)
- リビング滞在:100分
- ダイニング滞在:20分
- 使用した電化製品:テレビ、スマホ×4、タブレット×2、ノートパソコン、加湿器
- 延長コード使用:2本
1日で、コンセント関連の「不便」を11回感じていたんです。
「3秒ルール」と「3メートルルール」
行動ログから、もう一つの法則が見えてきました。
3秒ルール:コンセントまで3秒以内(約3歩)で到達できないと、「面倒」と感じる
3メートルルール:コンセントまでの距離が3メートルを超えると、延長コードを使おうとする
つまり、よく使う場所から3メートル以内、できれば1.5メートル以内にコンセントがないと、不便を感じるんです。
ホットスポット分析
行動ログを1週間続けると、「ホットスポット」が見えてきます。
ホットスポットとは、1日の中で長時間滞在し、かつ多くの電化製品を使う場所。
我が家のホットスポット:
1位:キッチン(1日平均120分滞在)
- 必要コンセント数:12口
- 実際の配置数:8口
- 不足数:4口 ←現在、延長コード2本で対応
2位:リビングのソファ周り(1日平均90分滞在)
- 必要コンセント数:6口
- 実際の配置数:4口
- 不足数:2口 ←現在、延長コード1本で対応
3位:主寝室のベッド周り(1日平均30分+就寝時間)
- 必要コンセント数:6口
- 実際の配置数:4口
- 不足数:2口 ←夫婦で取り合い状態
このホットスポットこそが、最優先でコンセントを増やすべき場所だったんです。

部屋別「最低ライン」と「快適ライン」の数字
「結局、各部屋に何個コンセントを付けたらいいの?」
これが一番知りたいことですよね。
3年間の実生活データから、私なりの「最低ライン」と「快適ライン」をまとめました。
玄関・廊下エリア
最低ライン:2口
- 掃除機用×1
- 予備×1
快適ライン:4口
- 掃除機用×1
- 充電ステーション×2
- 予備×1
私の評価:★★☆☆☆(最低ライン以下で後悔中)
リビング・ダイニング
最低ライン:家族人数×2+4口
- 4人家族なら12口
快適ライン:家族人数×3+6口
- 4人家族なら18口
実際の内訳:
- テレビ周り:6口
- ソファ周り:6口
- ダイニングテーブル周り:3口
- その他:3口
私の評価:★★★☆☆(最低ラインギリギリで時々不便)
キッチン
最低ライン:10口
- 冷蔵庫×1
- 常設家電(炊飯器、ケトル等)×5
- 調理家電用×3
- 予備×1
快適ライン:15口
- 上記に加えて
- パントリー内×3
- カップボード内×2
私の評価:★★☆☆☆(快適ラインに5口不足)
洗面所・脱衣所
最低ライン:家族人数+2口
- 4人家族なら6口
快適ライン:家族人数×1.5+3口
- 4人家族なら9口
実際の内訳:
- 洗面台周り×6
- 洗濯機周り×3
私の評価:★☆☆☆☆(最低ラインを大幅に下回る4口で毎朝ストレス)
主寝室
最低ライン:居住者数×3口
- 夫婦なら6口
快適ライン:居住者数×4+2口
- 夫婦なら10口
実際の内訳:
- ベッド右側×5
- ベッド左側×5
私の評価:★★★☆☆(最低ラインクリアだが快適ラインには届かず)
子ども部屋(小学生の場合)
最低ライン:6口
- 学習机周り×3
- ベッド周り×2
- その他×1
快適ライン:10口
- 学習机周り×5
- ベッド周り×3
- その他×2
私の評価:★★★★☆(快適ラインで設計、正解だった)
ワークスペース・書斎
最低ライン:8口
- PC本体・モニター×3
- 照明×1
- 充電器×3
- 予備×1
快適ライン:12口
- 上記に加えて
- 周辺機器×4
私の評価:★★☆☆☆(最低ラインで設計したが、在宅ワークの増加で不足)
トータル推奨数
延床面積30坪の4人家族の場合:
- 最低ライン:60口
- 快適ライン:85口
- 理想ライン:100口
私の家の実際:58口 ←最低ラインをわずかに下回る
これが、延長コードだらけの生活になった原因です。
「5年後の自分」をシミュレーションする技術
私が最も後悔しているのが、「今の生活」だけで判断してしまったことです。
家を建てた3年前、息子は3歳、娘は5歳でした。
「子ども部屋にコンセント? まだおもちゃで遊ぶだけだし、3つもあれば十分でしょ」
そう思っていました。
でも今、娘は小学3年生。息子は小学1年生。
子どもの成長で変わった電力需要
娘の部屋(現在8歳):
- 学校から借りているタブレット
- 自宅用タブレット
- 電子辞書
- デスクライト(学習用)
- ベッドライト(読書用)
- 電気毛布(冬)
- 扇風機(夏)
- 加湿器(冬)
必要コンセント数:8口 実際の配置数:3口 不足数:5口
結果:延長コード2本と電源タップで対応中。見た目も悪いし、安全面も心配。
「ライフステージ予測表」の作成
もし家を建てる前に戻れるなら、この表を作ります。
| 年 | 娘の年齢 | 息子の年齢 | 予測される変化 | 必要な電源対応 |
| 2021 | 5歳 | 3歳 | 家を建てる | 子ども部屋に各3口 |
| 2023 | 7歳 | 5歳 | 小学校入学 | タブレット×2追加 |
| 2025 | 9歳 | 7歳 | 学習机本格使用 | デスクライト×2追加 |
| 2027 | 11歳 | 9歳 | スマホ所持開始? | 充電スペース×2追加 |
| 2029 | 13歳 | 11歳 | 中学入学 | パソコン×2追加 |
| 2031 | 15歳 | 13歳 | 部屋で過ごす時間増 | 各種デバイス増加 |
この表があれば、「5年後には8口必要になる」と予測できたはずです。
「家電増殖曲線」という現実
もう一つのデータをお見せします。
我が家の家電数の推移:
- 2021年(新築時):32個
- 2022年(1年後):38個(+6個)
- 2023年(2年後):47個(+9個)
- 2024年(3年後):54個(+7個)
3年で1.7倍に増えています。
増えた主な家電:
- コーヒーメーカー
- ホームベーカリー
- 電気圧力鍋
- ロボット掃除機
- 空気清浄機×2
- 加湿器×3
- サーキュレーター×2
- 電動自転車×2(バッテリー充電が必要)
- スマートスピーカー×3
- プロジェクター(リビング用)
- ポータブル電源(災害対策)
「新しい家だから、新しい家電が欲しくなる」という心理。これは確実にあります。
在宅ワークの予期せぬ拡大
2021年、私は週1日だけ在宅ワークをしていました。
「書斎なんていらない。リビングのカウンターで十分」
そう思って、カウンター近くにコンセント4口だけ付けました。
でも2024年の今、私は週4日在宅ワーク。夫も週3日在宅ワーク。
必要になったもの:
- 外付けモニター×2
- ウェブカメラ×2
- 外付けマイク×2
- デスクライト×2
- ノートパソコン用スタンド(電動)×2
- 書類用スキャナー
- 小型プリンター
カウンターのコンセント4口では全く足りず、今は延長コード3本が床を這っています。
「変化対応余裕率30%」の法則
これらの経験から、私が導き出した法則があります。
今必要なコンセント数×1.3=実際に設置すべき数
例えば、今8口必要だと計算したら、実際には10〜11口設置する。この30%の余裕が、将来の変化に対応できる「余白」になります。
「見えないコンセント」という美学の追求
ここまで数の話をしてきました。でも、コンセントには「見た目」という重要な側面があります。
Pinterest の嘘
家を建てる前、私は Pinterest で何百枚もの写真を保存していました。
真っ白な壁、シンプルな家具、何もないスッキリとした空間。
でも、あの写真には映っていないものがあります。それが「コード」です。
実際に住み始めると、現実が見えてきました。
スマホの充電ケーブルが床を這い、ソファの裏から延長コードが顔を出し、テレビの後ろはコードの塊。
「写真と違う…」
その原因は、コンセントの「数」だけでなく「位置」にもあったんです。
高さの魔法
コンセントの標準的な設置高さは、床から25センチ。
でも、この高さが「すべての場所」で正解とは限りません。
キッチンカウンターの場合
- 標準高さ(床から25cm):炊飯器の上にコンセントが見える
- 調整後の高さ(カウンター天板から-3cm):炊飯器の背面に隠れて見えない
この「3センチの差」が、見た目を大きく変えます。
ベッドサイドの場合
- 標準高さ(床から25cm):ベッドから手を伸ばすのが大変
- 調整後の高さ(床から60cm):ベッドに横になったまま届く
この「35センチの差」が、快適さを大きく変えます。
ソファ周りの場合
- 標準高さ(床から25cm):ソファで隠れて使いにくい
- 調整後の高さ(床から50cm):ソファの背もたれから顔を出す
この「25センチの差」が、使いやすさを大きく変えます。
「コンセント隠蔽マップ」の作成
私が後から学んだ技術があります。それが「コンセント隠蔽マップ」。
各部屋で、コンセントを「見せる」「隠す」「半隠し」に分類するんです。
見せるコンセント
- 掃除機用(使うときだけ挿すので、見えても問題ない)
- 客間や廊下(使用頻度が低い)
隠すコンセント
- 家具の裏側(テレビボード、ベッド、ソファの裏)
- 収納内(パントリー、クローゼット内)
- 天井付け(エアコン用)
半隠しコンセント
- 家具の側面(サイドテーブルで半分隠れる)
- 腰壁の裏側(カウンター下など)
このマップがあれば、設計段階で「このコンセントは家具で隠れる位置に」と指定できます。
色の調和という視点
リビングの一面を、ダークグレーのアクセントウォールにしました。
とても気に入っていたのですが…引き渡しの日、その壁に真っ白なコンセントが4つ。
まるで「白い傷」のように目立っていました。
すぐにホームセンターへ走り、グレーのコンセントカバーを購入。交換したところ、ほとんど目立たなくなりました。
コスト:1個300円×4=1,200円
でも、これを建てる前に指定していれば、追加費用なし、またはわずかな差額で対応できたはずです。
間接照明とコンセントの共生
我が家で最も成功したのが、間接照明とコンセントの組み合わせ。
リビングの天井近く、壁の上部に間接照明用のコンセントを設置しました(床から200cm)。
この位置だと:
- 普段の視線からは見えない
- 間接照明のコードが壁を這わない
- 光が天井に反射して、部屋全体が明るくなる
結果、「コンセントがどこにあるか分からない」と友人に言われるほど、自然に溶け込んでいます。
「お金」と「快適さ」の天秤をどう考えるか
ここまで読んで、こう思ったかもしれません。
「そんなにたくさんコンセント付けたら、すごくお金かかるんじゃ?」
確かに、コンセントは無料ではありません。でも、その「投資対効果」を冷静に計算すると、実は非常にコスパが良いんです。
コンセント1口のコスト分析
新築時にコンセントを1口増やすコスト:
- 材料費:約1,000円
- 工事費:約2,000円
- 合計:約3,000円
建築後に1口追加するコスト:
- 材料費:約1,000円
- 工事費:約20,000円
- 壁の開口・修復:約15,000円
- 内装補修:約10,000円
- 合計:約46,000円
差額:43,000円
つまり、建てる前に追加しておけば、15分の1のコストで済むんです。
延長コードの「隠れたコスト」
「コンセント付けなくても、延長コード使えばいいじゃん」
実際、私もそう思って、コンセントを減らしました。その結果…
現在使っている延長コード:
- 6口タップ×3本=約9,000円
- 3口タップ×2本=約4,000円
- 延長コード(5m)×2本=約3,000円
- 合計:約16,000円
さらに、見えない コストがあります:
安全面のリスク
- 延長コードの踏みつけによる断線リスク
- タコ足配線による過熱リスク
- 子どもがつまずく危険性
美観の損失
- 床を這うコードが見苦しい
- 来客時に片付けるストレス
- 「こんな家じゃなかったはず」という心理的ストレス
時間的コスト
- コンセントの抜き差しの時間(年間約2時間)
- 延長コードの配線を考える時間
- 「もっとコンセントあれば」と後悔する時間
これらを考えると、新築時に3,000円払ってコンセントを増やす方が、圧倒的に合理的です。
「1コンセント1万円換算法」
私が後から気づいた計算方法があります。
コンセント1口 = 今後30年の快適さ = 価値1万円
つまり、3,000円で1万円の価値を買っているようなもの。
10口追加しても3万円。でも、得られる快適さの価値は10万円。
こう考えると、「コンセントは多すぎるくらいでちょうどいい」という結論になります。
優先順位の付け方
とはいえ、予算には限りがあります。だから、優先順位を付けることが大切。
私が考える優先順位:
最優先(絶対に削らない)
- 洗面所(毎朝使う、家族全員に影響)
- キッチン(毎日使う、追加家電が増えやすい)
- リビングのソファ周り(長時間滞在する)
- 寝室のベッド周り(毎日使う、快適な睡眠に影響)
高優先(できれば確保したい)
- 子ども部屋(成長で需要が増える)
- ダイニング周り(ホットプレート等で使う)
- ワークスペース(在宅ワークが増える可能性)
中優先(予算次第)
- 収納内コンセント(美観には良いが必須ではない)
- 玄関(使用頻度は低い)
- 廊下(掃除機用、あれば便利)
低優先(後回しでOK)
- トイレ内(温水洗浄便座用のみで十分)
- バルコニー(使用頻度がかなり低い)
この優先順位に従えば、限られた予算内でも、本当に必要な場所には十分なコンセントを確保できます。
3年間で学んだ「後悔しないための10の鉄則」
最後に、私の3年間の経験を10の鉄則にまとめました。
鉄則1:「今」ではなく「5年後」で計算する
今必要な数ではなく、5年後に必要になりそうな数を基準にする。子どもの成長、ライフスタイルの変化、テクノロジーの進化を考慮に入れる。
鉄則2:「最低ライン」ではなく「快適ライン」を目指す
「これだけあれば何とかなる」ではなく、「これだけあれば快適」を基準にする。差額はわずかでも、得られる満足度は大きく違う。
鉄則3:家族の「行動ログ」を24時間取る
図面だけで判断せず、実際の生活動線を記録する。どこで何をするか、どの電化製品をいつ使うかを具体的に把握する。
鉄則4:「ホットスポット」に重点投資する
すべての部屋を同じように考えるのではなく、長時間滞在する場所に重点的にコンセントを配置する。
鉄則5:コンセントの「高さ」を使い分ける
床から25cmの標準高さだけでなく、用途に応じて50cm、70cm、100cmなど、高さを変える。使いやすさと見た目が大きく変わる。
鉄則6:「隠す」ことを前提に配置する
家具の配置を正確にシミュレーションし、コンセントが家具の裏側に来るように設計する。見える場所のコンセントは最小限に。
鉄則7:「収納内コンセント」を積極活用する
パントリー、クローゼット、シューズクローゼットなど、収納内にコンセントを設置。生活感のある家電を隠しながら使える。
鉄則8:色の調和を忘れない
アクセントウォールや濃い色の壁には、コンセントの色を合わせる。わずかな投資で、見た目が劇的に改善する。
鉄則9:「迷ったら付ける」が正解
使うかどうか迷ったら、付けておく。建てた後に追加すると10倍以上のコストがかかる。使わなくても害はない。
鉄則10:設計士の提案を安易に断らない
設計士が「あった方がいい」と提案するのは、過去の経験からの助言。少なくとも理由を詳しく聞いてから判断する。
まとめ:コンセント計画は「未来への手紙」
新築から3年。私は今、この記事を書きながら、3年前の自分に手紙を書いている気分です。
「もっとコンセントを付けて」 「洗面所にあと3口追加して」 「子ども部屋は将来を考えて」
でも、タイムマシンはありません。私にできるのは、これから家を建てるあなたに、この経験を伝えることだけ。
コンセント配置は、地味です。壁紙やキッチンの設備に比べたら、ワクワクしません。
でも、毎日の生活の質を決めるのは、こうした「地味な部分」の積み重ねなんです。
毎朝のストレスゼロ 充電の順番待ちゼロ 延長コードゼロ 「あと1口あれば」という後悔ゼロ
そんな家は、実現可能です。
必要なのは、少しの投資と、たくさんの想像力。
あなたの新しい家が、毎日「ここにコンセントがあって良かった」と思える場所になりますように。
そして、3年後のあなたが、過去の自分に「ありがとう」と言える家になりますように。
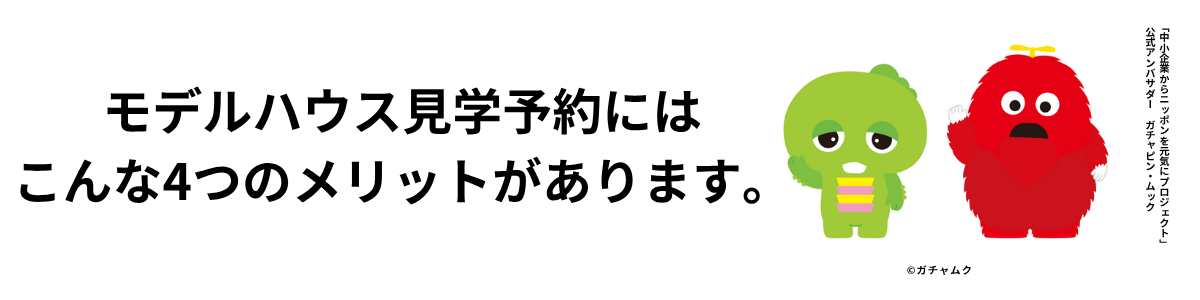
モデルハウス見学予約の
4つのメリット
✅ 1.サクサク見学
待ち時間なくスムーズに見学できるので、貴重な時間を有効活用できます。家族との大切な週末を有意義に過ごせます。
✅ 2.効率よく見学!
複数のモデルハウスをまとめて見学できるので、効率的に情報収集が可能です。自分に最適な住まいを一度に比較検討できます。
✅ 3.専門性の高いスタッフ
専門知識を持ったスタッフがあなたの要望に合わせて丁寧に対応。理想の住まいを見つけるためのアドバイスが受けられます。
✅4.当日のやりとりがスムーズ
事前に質問を伝えられるので、当日の見学がスムーズに進みます。重要なポイントをしっかり確認でき、安心して見学が楽しめます。