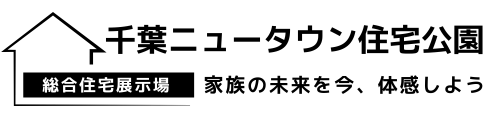「相続なんてまだまだ先の話」と思っていても、親の住まいや土地のことが少しずつ気になり始めた……そんなタイミングこそが準備のしどきです。特に注意したいのが、家の相続にまつわるトラブルや費用の問題。実は、相続の前にリフォームを行うことで、住み心地をよくするだけでなく、“節税効果”が得られるケースもあるんです。
この記事では、相続税の仕組みとリフォームとの関係、損しないための考え方や注意点を、わかりやすくご紹介します。家族で安心して未来を迎えるために、今できる備えを一緒に考えてみませんか?
この記事を読めばわかること:
- 相続税の計算と不動産評価の仕組み
- リフォームが相続税にどう影響するか
- 節税に有効なリフォームと注意が必要なケース
- 相続前にやっておきたい3つの準備ステップ
1. 相続税の計算、そのカギを握るのは“資産の合計”
相続税は、亡くなった方が残した遺産の“総額”をもとに決まります。基礎控除という一定の非課税枠があるため、すべての人に相続税が課されるわけではありません。
基礎控除額の計算式: 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
この控除額を超えた部分に税金がかかるのですが、そこでカギを握るのが「不動産の評価」です。現金や預金とは違って、不動産は評価が難しく、築年数や立地によって税務上の価値が大きく変わります。中でも、古い家ほど「どう評価されるか」でトラブルになりやすいのです。
2. 建物の評価は“固定資産税評価額”で決まる
不動産の中でも、建物の評価には「固定資産税評価額」が使われます。これは毎年市区町村が評価している金額で、実際の売却価格(実勢価格)とは異なります。
押さえておきたいポイント:
- 建物は年数が経つほど評価が下がる(減価償却)
- 木造よりもRC造(鉄筋コンクリート造)の方が評価が高め
つまり、「古くてボロボロの家でも高く見積もられるのでは…?」という心配はあまり必要ありません。ただし、ここにリフォームが絡んでくると、話は少し複雑になります。
3. リフォームが評価額に影響する場合・しない場合
リフォームは内容によって、評価額に「ほとんど影響しない」場合と「大きく影響する」場合に分かれます。
【評価額に影響しにくいリフォーム】
- 古くなった水回り(キッチン・浴室など)の交換
- 外壁・屋根の塗装、雨漏り対策などの修繕工事
- バリアフリー化や断熱性能アップなど、生活の質向上を目的とした改修
これらは“建物の価値を元の状態に戻すため”とみなされ、評価額のアップにはつながりません。つまり、住みやすくなるうえに節税効果もあるという、うれしいリフォームです。
【評価額が上がる可能性のあるリフォーム】
- 建物の増築や間取り変更で延床面積が増える工事
- 高級素材やデザイン性を重視した大規模な内装リノベーション
- 太陽光パネルや蓄電池の新設など、設備の追加
これらは“建物の資産価値を向上させる”と判断されるため、固定資産税評価額も上がり、結果として相続税も増えるリスクがあります。
つまり、「リフォーム=節税」ではなく、「内容による」というのが正確な見方です。

4. リフォーム費用で相続財産を“減らせる”って本当?
意外と知られていませんが、リフォームにかけたお金が“相続税を減らす”という観点もあります。
例えば:
- 親の貯金でリフォーム費用を支払えば、その分現金が減り、相続時の課税対象額が下がる
- 評価額に影響しないリフォーム内容であれば、建物の価値は据え置き → 相続財産全体は減る
これは、うまく活用すれば節税に直結します。ただし、過剰に高額な工事や目的が不明瞭な場合、「意図的な課税回避」と見なされるおそれも。
節税目的でリフォームする場合の注意点:
- 相場と比べて“適正な工事費用”であること
- 工事内容に実態があり、生活改善に根拠があること
節税を狙うなら、「グレーゾーンにならない設計と実行」が重要。専門家の意見を取り入れることで、リスクを回避できます。
5. 見落としがちな“贈与”扱いのリスク
「親の家を子どもが自費でリフォームしてあげた」というケース、一見ほほえましく見えても、実は“贈与税”の対象になることがあります。
【税務上の落とし穴】
- 親名義の家を子どもがリフォームし、その費用を子が負担すると「親への贈与」と見なされることがある
- 年間110万円を超える贈与は申告義務がある(基礎控除の範囲を超えると課税)
また、親が「将来子に譲るつもりで」とリフォーム代を出した場合でも、名義やタイミング次第で贈与と判断されることがあります。
相続と贈与の線引きは非常に曖昧。 少しの違いで課税対象になるリスクがあるため、あらかじめ税理士などの専門家に確認しておくのがベストです。
6. 相続前にやっておくべき3つの準備ステップ
リフォームを含めた“相続対策”を考えるなら、早めの行動がカギ。以下の3ステップで、スムーズな相続に備えましょう。
【STEP1】現状の把握
- 家の構造や築年数を確認
- 固定資産税評価証明書を取得
【STEP2】リフォームの目的整理
- 生活改善? 節税対策? 目的を明確に
- 優先順位をつけて必要な工事を検討
【STEP3】専門家への相談
- 税理士・不動産鑑定士・ファイナンシャルプランナーなどに事前相談
- 補助金や税制優遇制度の確認も忘れずに
まとめ
リフォームは、ただ家をきれいにするだけではなく、相続税の節税にもつながる“戦略的な手段”になり得ます。ただし、すべてのリフォームが節税になるわけではなく、その内容・名義・費用の支払い方などに注意が必要です。
「知らなかった」では済まない税の話──だからこそ、早めに行動し、専門家の力を借りながら備えておくことが、将来の安心につながります。
住宅展示場では、相続やリフォームに関する無料相談会を実施しているケースもあります。気になる方は、一度足を運んでみてはいかがでしょうか。
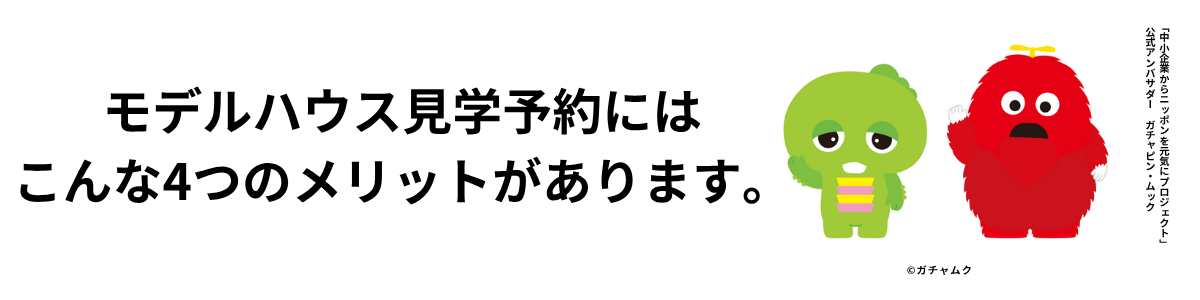
モデルハウス見学予約の
4つのメリット
✅ 1.サクサク見学
待ち時間なくスムーズに見学できるので、貴重な時間を有効活用できます。家族との大切な週末を有意義に過ごせます。
✅ 2.効率よく見学!
複数のモデルハウスをまとめて見学できるので、効率的に情報収集が可能です。自分に最適な住まいを一度に比較検討できます。
✅ 3.専門性の高いスタッフ
専門知識を持ったスタッフがあなたの要望に合わせて丁寧に対応。理想の住まいを見つけるためのアドバイスが受けられます。
✅4.当日のやりとりがスムーズ
事前に質問を伝えられるので、当日の見学がスムーズに進みます。重要なポイントをしっかり確認でき、安心して見学が楽しめます。