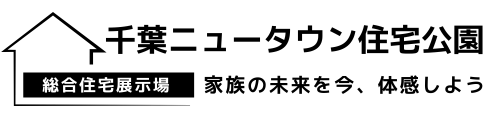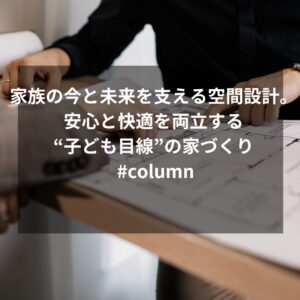「家を建てたいけど…正直、予算のことを考えると頭が痛い」
そんなあなた、安心してください。間取りやデザインを考える前にやるべきなのは、実は“お金の整理”なんです。
今回は、住宅資金の全体像からローンの選び方、使える優遇制度まで、ドタバタせずにスタートできる“資金計画のススメ”を、ゆるっとわかりやすく解説します!
この記事を読めばわかること
✔ 注文住宅にかかる費用の種類と中身
✔ 自己資金ってどれくらい必要なの?
✔ 住宅ローンの基本ルールと選び方
✔ 実は知られてない?優遇制度や補助金
✔ 「あれ、足りない…」とならない資金計画のコツ
1. 注文住宅って、いくらかかるの?
「坪単価〇〇万円」って聞くと、“それだけ払えばOK”と思いがち。でも実際には、いろんな費用が折り重なってます。ざっくり分けると、こんな感じです。
🏠 本体工事費
言わば「家そのもの」のお金。壁、床、屋根、設備…ぜんぶまとめた価格です。
→ 坪単価は参考程度に。オプションであっという間に上がります。
🚧 付帯工事費
地盤調査、外構、ガスや水道の引き込みなど「暮らせる家」にするための裏方費用。
→ 見積もりから漏れがち。でも数十〜数百万円かかることも。
🧾 諸費用
登記・火災保険・ローン手数料・印紙代…などなど、「事務的だけど外せないやつら」。
→ だいたい総費用の5〜10%くらい見ておくと安心。
🪑 家具・家電・引っ越し代
え、そこまで入ってないの?というのがリアル。
→ 冷蔵庫・エアコン・カーテンとか、買い直すものが案外多い。

2. 自己資金、いくらあれば足りるの?
「頭金ってやっぱり必要?」という疑問、よく聞きます。
🔍 目安は総予算の2〜3割
もちろんゼロでもローンは組めますが、利息や毎月の返済負担を減らすためにも、20〜30%くらいあると心強いです。
💰 自己資金の中身はこんな感じ
- 貯金:使ってOKな自由なお金
- 贈与:親からもらえるなら、非課税枠を活用!
- ボーナス:あてにしすぎるのはNG。余裕があるときだけ。
ポイントは、“出せる金額”と“出していい金額”は違う、ということ!
3. 住宅ローン、ざっくりどう選べばいい?
「住宅ローンって、沼では?」…そう感じるのも無理ありません。でもポイントを押さえれば、意外とスッキリします。
💡 借入額は“借りられる額”じゃなく“返せる額”
- 月収の25〜30%以内が目安
- 将来の教育費や老後資金も加味して考えよう
📈 金利のタイプは3つ
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 固定金利 | ずっと同じ金利で安心。予算を立てやすい。 |
| 変動金利 | 初期は低金利。でも途中で上がる可能性あり。 |
| 固定期間選択型 | 最初の数年だけ固定→その後は再選択 or 変動。 |
「安い方」で選ぶのではなく、「どれが自分の暮らしに合うか」で選ぶのがコツ。
4. もらえるお金・戻ってくるお金をチェック!
使える制度は、使い倒す!これ、資金計画の鉄則です。
💸 住宅ローン控除
- 年末のローン残高の0.7%を10〜13年、所得税から控除
- 年度によって条件や上限が変わるので要チェック!
🎁 住宅取得資金の贈与非課税制度
- 親や祖父母からの資金援助に、最大1,000万円の非課税枠(条件あり)
🏘 地方自治体の補助金
- 子育て世代支援や移住促進で出している自治体も!
- ZEH補助金など、エコ住宅向け制度もチェック!
5. 資金計画で「やっちまった」を回避するには?
「予算オーバーしました…」というのは、正直あるある。じゃあどうすれば防げる?
✅ 予備費をしっかり確保
→ 10〜15%は“予備”として残しておこう!
✅ 全部の費用を“見える化”する
→ 頭の中だけじゃダメ。エクセルでも紙でも、とにかく書き出す!
✅ 契約前に“生活後”まで想像する
→ 「このローン、子どもが大学行ったあとでも払える?」みたいな視点も大事!
まとめ
お金の計画って、ちょっと難しそうだけど、実は「知らなかった…」が一番怖い。
家を建てる前に、人生そのものを見渡してみる。そんな気持ちで資金と向き合えば、きっと後悔のない一歩が踏み出せます。
「未来の暮らし」にワクワクしながら、今日から始めてみませんか?
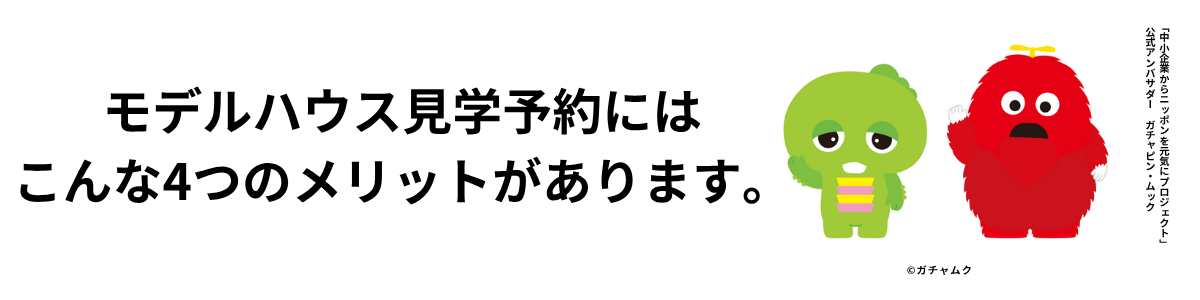
モデルハウス見学予約の
4つのメリット
✅ 1.サクサク見学
待ち時間なくスムーズに見学できるので、貴重な時間を有効活用できます。家族との大切な週末を有意義に過ごせます。
✅ 2.効率よく見学!
複数のモデルハウスをまとめて見学できるので、効率的に情報収集が可能です。自分に最適な住まいを一度に比較検討できます。
✅ 3.専門性の高いスタッフ
専門知識を持ったスタッフがあなたの要望に合わせて丁寧に対応。理想の住まいを見つけるためのアドバイスが受けられます。
✅4.当日のやりとりがスムーズ
事前に質問を伝えられるので、当日の見学がスムーズに進みます。重要なポイントをしっかり確認でき、安心して見学が楽しめます。